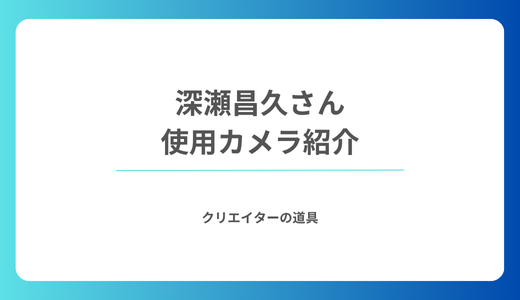日本写真界において異彩を放つ表現を追求し続けた深瀬昌久氏。「私性」と「遊戯」をテーマに、家族やカラス、猫といった身近な被写体を通じて独自の写真世界を構築した彼の作品は、今なお多くの写真家に影響を与え続けています。そんな深瀬氏の創作を支えたカメラ機材には、どのような特徴があったのでしょうか。彼が実際に使用していた機材を詳しく紹介します。
深瀬昌久さんの紹介
深瀬昌久(ふかせ まさひさ、1934年2月25日 – 2012年6月9日)は、日本の写真表現に革新をもたらした写真家です。北海道中川郡美深町で1908年に祖父が創設した深瀬写真館の長男として生まれ、幼少期からプリント水洗の仕事を手伝わされた経験が、後の写真への複雑な感情を育むことになりました。
日本大学芸術学部写真学科で学んだ後、第一宣伝社、日本デザインセンター、河出書房新社を経て、1968年にフリーランスの写真作家として独立。妻の鰐部洋子を被写体とした『遊戯』や、カラスを主題とした代表作『鴉』など、「私性」を深く掘り下げた作品群で高い評価を獲得しました。
1992年の転落事故により作家活動が中断されたものの、2014年の深瀬昌久アーカイブス設立を機に再評価が進み、現在では世界的に注目される写真家として位置づけられています。彼の40年にわたる作家活動をまとめた写真集『MASAHISA FUKASE』(2018年)や、瀬戸正人による『深瀬昌久伝』(2020年)の刊行により、その全貌がより詳しく紹介されています。
深瀬昌久さんが使用していた機材
ミノルタ new SR-1
深瀬昌久氏が東京で写真家として活動を始めた初期に愛用していたのが、ミノルタ new SR-1です。1965年に発売されたこの35mm一眼レフカメラは、ダイキャスト四角ボディとSRバヨネットマウントを採用し、セルフタイマーとミラーアップ機構を装備。シャッター最高速1/500秒の完全機械式カメラとして、過剰な機能に頼らない純粋な写真表現を可能にしました。シンプルでクラシックなミノルタの小文字ロゴが印象的で、深瀬氏の人物撮影や日常のスナップに重要な役割を果たしていました。
ペンタックスSPF
ミノルタ new SR-1の後に深瀬氏が手にしたのが、1973年発売のペンタックスSPFです。ペンタックスSPシリーズの進化系として「初のTTL開放測光」を搭載し、M42マウントにSMC(Super Multi Coated)対応の改良を加えました。シャッター最高速1/1000秒の機械式シャッターと、ホットシュー搭載により外付けフラッシュも使用可能。SMC Takumarレンズ使用時の開放測光機能は、現代デジタル一眼にも通じる先進技術でした。1970年代前半の深瀬氏の多様な被写体撮影に活躍した機材です。
リンホフ(ラージフォーマットカメラ)
商業撮影や広告写真の分野で深瀬氏が使用していたのが、ドイツ製の大判カメラ・リンホフです。代表機種であるリンホフ・マスターテヒニカは4×5インチ大判フィールドカメラの最高峰として知られ、レンズボード交換式でピントグラス使用、シフトやティルトなどのアオリ撮影にも対応。高品質な素材と仕上げによる絶大な信頼性で、大手家電メーカーの掃除機広告などのプロフェッショナル撮影において、細部まで高精細に描写する能力を発揮しました。
コニカ ビッグミニ
1992年の作品シリーズ『私景’92』で深瀬氏が使用したのが、コニカ ビッグミニです。1989年に発売されたこのコンパクトAFフィルムカメラは、沈胴式レンズ採用により非常に薄型かつ軽量を実現。全自動露出とAF搭載で「押すだけで写る」操作性を持ち、ポケットにも収まる携帯性が特徴でした。深瀬氏はこのカメラを使い、ノーファインダーで自分の顔や手、足をフレームに入れて撮影するという実験的なアプローチを行いました。90年代のコンパクトカメラブームを代表する機種として、スナップ撮影の新たな可能性を示した機材です。
アサヒペンタックス SUPER-LITE II型
ペンタックスSPFとセットで使用されていたのが、アサヒペンタックス SUPER-LITE II型クリップオンフラッシュです。ペンタックスSPシリーズ対応の純正クリップオンフラッシュとして、アクセサリーシューに装着することで純正ボディとの自然な一体感を実現。当時のカメラに合わせたデザインと適切な光量により、深瀬氏の夜間撮影や暗所でのスナップ撮影において重要な役割を果たしました。ペンタックス純正アクセサリーとしての使い勝手と信頼性の高さが評価された機材です。
まとめ
深瀬昌久氏が使用していた機材を見ると、時代の変遷とともに彼の表現手法が進化していったことがよくわかります。初期のミノルタ new SR-1やペンタックスSPFといった機械式一眼レフから、商業撮影用のリンホフ大判カメラ、そして実験的な表現を可能にしたコニカ ビッグミニまで、それぞれが深瀬氏の創作活動の重要な局面を支えていました。
特に注目すべきは、高級機材だけでなく、コンパクトカメラのような身近な機材も積極的に取り入れ、そこから新しい表現を生み出していた点です。これは「私性」と「遊戯」を追求した深瀬氏らしいアプローチといえるでしょう。現在でも中古市場で入手可能なこれらの機材は、写真表現の可能性を広げたい方にとって、深瀬昌久という偉大な写真家の足跡を辿る貴重な手がかりとなるはずです。
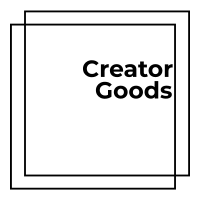 クリエイターの道具
クリエイターの道具